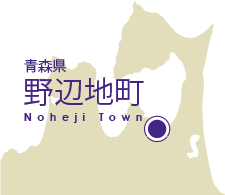近くのスポット
近くのスポット
江戸日本橋を起点とし、三六町を一里として一里ごとに街道の両側に土を高く盛り、その上に樹木を植え、里程標としたものです。この一里塚は奥州街道上につくられたもので塚と塚の間には街道のあとが残されています。
※一町は約109.09m。

旧旅館であったこの建物は、明治33年(1900年)に建てられた和洋折衷の貴重な近代和風建築です。
1988年にはフジテレビドラマ「飢餓海峡」の撮影場所として使用されました。
なお、建物内の見学は不可となっています。

城内(現中央公民館地内)にありました。
代官はおおむね盛岡直参の藩士が任命され任期は通常2ヵ年程度でした。
元々の野辺地代官所の建築年代は明らかではありませんが、建物の配置図は残っています。

最上徳内〈宝暦4年(1754年)~天保7年(1836年)〉は、江戸時代の探検家で江戸幕府普請役。出羽国村山軍楯岡村(現在の山形県村山市楯岡)出身です。徳内は、2回目の蝦夷地行きを松前藩に断られ、南部領野辺地に留まり2年間船頭新七の家で算術・読み書きを教えていました。その間に、廻船問屋を営む嶋屋清吉の娘(ふで)と結婚しました。徳内は82歳で亡くなるまで数々の著作を残しています。

【街かどに立つ標柱を探してみよう!】
江戸時代、この一帯は盛岡藩の同心の屋敷15軒が道の両側に続いていたことから、御同心丁あるいは御組丁と呼ばれていました。
御同心丁をはさんで道は大きく折れていますが、北から攻撃されたとき、敵が町に一直線に侵入するのを防ぐためと思われます。

街かどに立つ標柱を探してみよう!
大砲台場は、盛岡藩によって安政3年(1865年)に築造され、外国の船に備え大砲が置かれていました。現在の新道は、この工事のために作られた道路です。明治元年(1868年)の戊辰戦争のとき、野辺地を艦砲射撃した新政府軍の船(陽春丸)に対し、藩ではこの台場から反撃しています。新政府軍の砲撃は50~60発で常光寺の大杉や各所に着弾しましたがいずれも爆裂はしなかったといわれます。一方台場からは、17~18発発射し帆柱と船体中央に2発命中し、陽春丸は慌てて退散しました。

街かどに立つ標柱を探してみよう!
江戸時代、この一帯には盛岡藩の銅蔵や大豆蔵、野辺地の商人の土蔵や板蔵があったことから蔵町と呼ばれています。蔵に納められた大豆・鰯しめ粕、銅などの南部領内の産物は、北前船によって大坂や北陸などの日本海航路上の湊に運ばれていきました。

街かどに立つ標柱を探してみよう!
江戸時代、この場所には盛岡藩によって設置された遠見番所がありました。江戸幕府は外国との通商を禁止していたことから外国船の出入や通過を監視するために設けられた施設です。

街かどに立つ標柱を探してみよう!
御番所は、江戸時代に盛岡藩によって設置され、人々や物資の出入を監視していました。建物は柵で厳重に囲われ役人が警護していました。この番所から西へ約2kmには南部領と津軽領との境界につくられた藩境塚があります。